

佐方 八幡神社

我がふるさと 佐方という地名の成り立ち
| 廿日市市内の東の端の地域が佐方です。 |
| 元和五年(1619)のころは、坂田村といい、その後佐方村となり、明治二十二年 |
| (1889)に合併して観音村となり、昭和三十一年に五日市町に合併。 |
| さらに昭和三十二年に廿日市町に合併と佐方は廿日市と密接な関係がある。 |
| 今から180年前の文政年間の広島藩の記録「芸藩通志」によれば、佐方は昔は |
| 坂田で、そのもとは尺田か狭潟であったろうと記されている |
| その昔(中世以前)は、洞雲寺の前あたりまで海が入り込み、佐方八幡宮の前 |
| あたりが海辺で狭潟(遠浅の海の地形)となっていた。 |
| 江戸時代の初めに海岸線沿いの西国街道が整備され、その道路敷きが堤防 |
| の役割を果たして、広い干拓地が形成された。 |
| 180年前の文政八年(1825)の戸口変遷によると、 |
| 廿日市エリア 665戸 2,845人 |
| 佐方 159 738 |
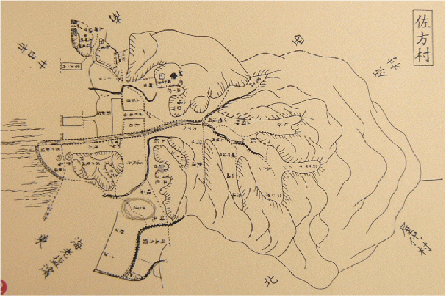
佐方 八幡神社 (1)
| 文政八年(一八二五)約180年前に完成の廣島藩領内の地理や歴史を記した |
| 『芸藩通志』によれば、佐方 八幡宮は今から400年前に、毛利家より神田の寄 |
| 進があったらしいこと。 |
| また700年前からこの地方佐伯郡一円の領主であった桜尾城主、厳島神社の |
| 神主家であった藤原氏が崇拝していた社で、この神社の祭主だったことが記さ |
| れています。 |
| 農耕の神で佐方の氏神(古代の氏族が共同でまつった祖先神)である木造神像、 |
| 薬師如来坐像が祀られています。 |
| 拝殿には三十六歌仙額が奉納されています。 一般に三十六歌仙額が描かれた |
| 時代は、平安時代末から鎌倉時代初めと考えられ、絵師は不明とされています。 |
| 江戸時代、佐竹藩(秋田県)所蔵の「佐竹本 三十六歌仙絵巻」を和歌と絵で板に |
| 描かれた板絵の額、「絵額」のことです。 |
| 写真は奉納されている一部の絵額です。 |  |
| 藤原清正 | |
| 「子の日しにしめつる野辺の のひめこ松引かでや千代のかげを待たまし」 |
|
| 神社等に奉納される三十六歌仙額は絵馬のように | |
| 「家内安全、商売繁盛、受験合格とか」の願い文 | |
| はない。 奉納者の真の願い事はなんであったの | |
| かは、絵額が奉納された時代を読み取り、推測 | |
| するしかないのです。 | |
| いま時代の経過とともにで風化が激しく、見えにくく | |
| なっている絵額がほとんどです。 |
佐方 八幡神社 (2)
堀田仁助寄進の石燈籠 ーふるさと廿日市を想う仁助の心-
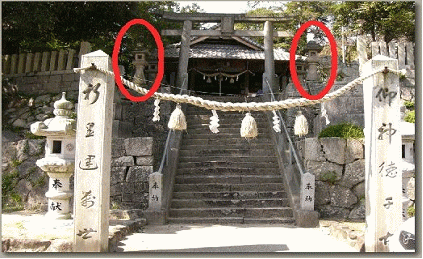
石灯籠の銘文
| 文化五年威辰年四月十一日建之 | |||
| 天文生堀田仁助藤原泉尹 |
| 石灯籠に刻まれた「天文生堀田仁助」の銘に天文・地理に命をかけた仁助の |
| 意志の強さと誇りを感じると人は言う。 |
| 仁助がこの石灯籠を寄進したのは文化五年(1808)六十一歳、幕府の天文方 |
| にいた時でした。 |
| 仁助にとっては、少年時代を過ごした好きなふるさと廿日市を誇りに想い、遠く |
| 江戸から、西の空のかなたのふるさと廿日市を決して忘れてはいなかったのです。 |
| いつの時代でも、幾つになっても、ふるさとを想う心は持ち続けたいものです。 |
| 堀田仁助寄進の石燈籠の下側に津和野藩御船屋敷の人物田原氏寄進の狛犬 |
| 一対がある。廿日市市内の潮音寺、正蓮寺、蓮教寺などにも津和野藩御船屋敷 |
| と縁浅からぬ墓が見受けられます。 |