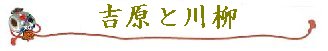
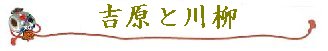
| トップ > 特集1 > 江戸の文化いろいろ> 吉原と川柳15 |
| 江戸一の大歓楽街 -吉原と川柳- |
| その拾伍 |
| 待乳山今では猪牙の目あてなり |
| 待乳山は眞土山とも云ひ、金龍山本龍院と称して、聖天宮を安置せしところで、この山の森は |
| 本所深川辺が未だ海であった頃、其方面から津入りする船の目標となったものである。 |
| 但し、今は吉原へ通ふ猪牙船の目あてになったと、時代の変遷を匂はした句である。 |
| ◇待乳山(まっちゃま)・・・浅草にある、隅田川に臨み、上野の台地に続く小高い丘。 |
| また、この門に名前は、物として米饅頭(よねまんじゅう)を鬻(ひさ)ぐ・・・商う・・・店があったと |
| 伝えられている。 |
| 聖天は船と駕との相の山 |
| 待乳山は、隅田川の右岸に存在するが故に、吉原への陸と水路の丁度中間にはさまれている |
| のであった。 聖天とは、天竺の神、大聖歓喜天の略称だと云われている。 |
| 三圍でひぐらしの鳴く好い時分 |
| 三圍稲荷(みめぐりいなり)は、隅田堤小梅村の田の中に在って、田中の稲荷とも云った。 |
| 別当三圍山眞珠院延命寺と号して、弘法大師が神像を刻み、大師が勧請されたもので、 |
| 彼の江戸座の俳人・其角が雨乞いの句を詠んだ有名な稲荷である。 |
| 向島へ郊外散策に行った戻りがけでもあろうが、川の面を紅に染めなす夕陽が、やがて |
| 聖天の森にかくれて、今戸あたりの瓦焼く烟(けむ)りが薄紫にたなびく頃、どこかに慌ただ |
| しい茅蜩(ひぐらし)が鳴き初め、丁度、吉原へ行くには、いゝ時分だと云ふ意である。 |
| なにゝせへ向ふへ越せと隅田川 |
| 白鬚の邊から持病再発し |
| いゝ年で然らばと云ふ隅田川 |
| 四季のをり々、この向島へ遊ぶものは、場所が廓に近い為め、自然と歓楽境へ吸はるゝが |
| 如く、流れ込むのであった。 |