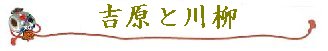
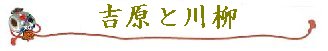
| トップ > 特集1 > 江戸の文化いろいろ> 吉原と川柳14 |
| 江戸一の大歓楽街 -吉原と川柳- |
| その拾肆 |
| 葬禮の戻りに不埒至極なり |
| 吉原へ廻らぬものは施主ばかり |
| 其数珠は仕舞ってくれと土手で云ひ |
| 山谷界隈には一帯に寺院が多く、葬禮の戻りに不埒(ふらち)にも、若い連中が生きた菩薩 |
| の済度(さいど)をうけに廻り道をするのであった。 |
| ◇済度(さいど)・・・・衆生(しゆじよう)を苦海から救い、彼岸へ導くこと。 |
| これで汚れが浄まると大一座 これでけがれがきよまるとおおいちざ |
| 焼香の順にと笑ふ大一座 |
| 大一座今日の佛とくちばしり |
| 葬禮くづれの大一座は、落語の題材となるべき、頗(すこぶ)る滑稽なものであった。 |
| ◇大一座(おおいちざ)・・・・特に、遊里や料亭などで、一団となってくり込んだ多人数 |
| の遊客。 |
| 大一座黒豆のある反吐をつき |
| 往昔(むかし)、葬禮には黒豆入りの白い強飯(こわめし)と煮〆を会葬者に出すのが例であったが、 |
| 六十歳以上の人が死んだ場合には、長命をして芽出度いと云ふ意味で、普通の赤飯を出したと |
| 云ふ。 |
| 大一座焼場の分も二人揚げ |
| 焼場へ廻った者も共に遊ぶ約束になっていて、先へ行ったものが、それらの人の敵娼(あいかた) |
| を揚げて置くと云ふ意である。 |