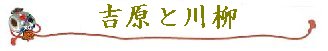
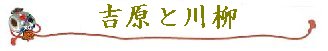
| トップ > 特集1> 江戸の文化いろいろ > 吉原と川柳13 |
| 江戸一の大歓楽街 -吉原と川柳- |
| その拾参 |
| 北国の片腕になる正燈寺 |
| 禅寺はいゝ方角の紅葉なり |
| 正燈寺は、龍泉寺町にある禅寺で、境内には、紅葉樹多く名所としてしられたところで、 |
| 此処の紅葉は、最初高雄より苗を移植せしものと伝へられている。 |
| 明和、安永の頃、紅葉と云えば、直に正燈寺を思い起こすほど有名なものであった。 |
| 此寺の紅葉が、何故、斯くの如く繁昌したかと云うに、吉原に近いからで、多くの遊蕩分子 |
| が、紅葉狩りと称しては、歓楽境へ流れ込む為であった。 |
| 吉原は紅葉踏み分けゆくところ |
| 今日こそは眞の紅葉と母へ云ひ |
| この正燈寺を、皆、口実にしたことが解かる。 |
| 眞間から見れば正燈寺遠いとこ |
| 眞間(まま)とは、葛飾の里の市川在で、紅葉の名所として知られし眞間山弘法寺の所在地 |
| である。此処へ来るものは、眞に紅葉を観賞する人々のみであって、江戸より日帰りの出来 |
| るところであるが、正燈寺への紅葉見物は、自然吉原へ泊まることになり勝ちなので、遠い |
| 場所だと、皮肉に逝ったのである。 |
| 正直な紅葉は足に豆が出来 |
| 嘘でない紅葉は二度と見にゆかず |
| 実際見物にゆく紅葉は、足に豆が出来るほど遠方なので、二度と決して見に行かないと云う意。 |
| 眞崎はこゝまで来てと云ふ所 |
| 眞崎の稲荷お先につかはれる |
| 眞崎稲荷(まつさきいなり)は、隅田川の右岸北の方に在って、元千葉之助常胤の居城、石濱 |
| 城内の守護神として崇められ、常胤(つねたね)が先陣魁け(せんじんさきがけ)の願書を内陣に |
| こめて祈願せし為、戦場に於て抜群の功名数度に及びたるが故に、「眞先」と号せしを、後年 |
| 「眞崎」と云ひかへられしものと伝へられている。また、拝殿の軒近く神木として榎(えのき)の |
| 大樹がある。これは、社殿建立の際、他の適当なる場所へ移さんとせしも、神意に反くとあって |
| 移植をしなかったと伝へられている。 |
| この眞崎稲荷も、正燈寺と同じように、こゝへ参詣の戻りや又参詣と称して、吉原へ足を向ける |
| ものが多かったのであった。 |
| 田楽ぢや飲めぬが事の始めなり |
| 田楽の足手まと゛ひは女づれ |
| 眞崎の田楽味噌のつけ始め |
| 社の附近には、宝暦の頃から田楽茶屋が出来て相当に繁昌したものであった。 |
| 眞崎で股がすくみんしたと云ふ |
| 遊女を連れて遊び半分参詣に来る嫖客(ひょうきゃく・・・うかれきゃく)が多く、歩き馴れない |
| 遊女のくたびれた様を詠んだものである。 |
| 江戸時代の遊女の廓言葉(さとことば)なるものとして、次のような特種の用語がある。 |
| ◆すくみんした・・・・・竦む(すくむ) ◆ありんす・・・あります ◆知りんせん・・・知らぬ |
| ◆さうざます・・・左様です ◆わちき・・・私 ◆来なまし・・・お出でなさい |